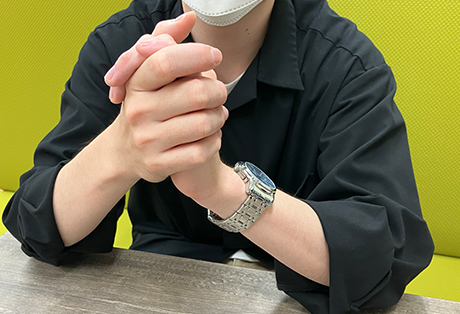パーソルグループの特例子会社、パーソルダイバースでは障害のある社員の半数以上が精神障害者手帳を持つ精神、発達障害のある社員です。
グループの事務アウトソーシングを請け負う受託サービス第1本部ではたらく森田さんもその一人。森田さんは入社4年目。ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠陥・多動症)という発達障害と向き合いながら、日々仕事を積み重ね、3年目には複数の社員の勤怠管理や業務割り振りを行う、「サブリーダー」という役職に就きました。「仕事を通じて社会に居場所がある喜びを感じる」と笑顔で話す森田さんから、仕事と障害の向き合い方、キャリアの重ね方を聞いてみました。

パーソルダイバース株式会社
受託サービス第1本部
PRO受託事業部 ビジネスサポート第3グループ
オーダーサポート第2チーム サブリーダー
森田 起恵
仕事や生活で感じる辛さ・・・原因は発達障害の症状だった

編集部:改めて、障害が分かった経緯を教えてください。
森田さん:子供のころから遅刻や忘れ物が多いとは思っていましたが、明確に自分自身に疑問を感じたのは、大学卒業前後の2015年くらいからです。正社員にはなれず、卒業後はアルバイトをしていました。そこでも集中しすぎて周りが見えなくなったり、接客が苦手で人と接することがうまくできなかったりと、辛い日々を送っていました。
あるとき、テレビを見たときに発達障害の特集をやっていて、「あれ、これ私あてはまるかも」と思い、2019年に通院したところ、発達障害の診断を受けました。診断を聞いて、生きづらさや、いろいろな場面でうまくいかないのは“甘え”や“なまけ”ではなく「障害」が理由なんだとわかり、ホッとしたことを覚えています。
実際、通院を始めて薬を飲むようになると症状が劇的に改善されました。私は感覚過敏で、ほかの人より周囲の音が大きく聞こえ、光をまぶしく感じるのですが、それがなくなったんです。服薬してはじめて「あ~、普通の人はこんなに静かな世界で生きているんだ」と感じました。
ASDとADHDである自分に合った仕事を探し、パーソルダイバースに入社
編集部:パーソルダイバースに入社するまではどのように過ごしたんですか?
森田さん:服薬で症状が落ち着いたので、まずは自分の障害を受け入れて、「サポートを受けながら仕事をする」という目標を立てました。自分の自己分析をして、自分のできること、できないことを明確にして、そのうえで「私がはたらくうえで必要なことは何か?」を整理しました。
出てきた答えは、「自分はデスクワークの仕事をするのが向いている」ということでした。
私にとってはたらくことは“社会に居場所を作ること”。そのため、「やりたい仕事」よりも「できる仕事」を選ぶことが大切でした。私は立って仕事をすると、血圧が下がり体調が悪くなるという特性もあります、またアドリブ対応が求められる接客業も特性上難しい。そこで、定例作業で座ってできるデスクワークの仕事を目指すことにしました。
デスクワークができるようになるために、就労移行支援事業所に1年間通って、PCスキルを身につけました。また、訓練の中で、面接でも自分が言いたいことをきちんと言えるように、言いたいことの要点をまとめ、模擬面接を繰り返すなどして、「自分の思いをきちんと話せる状態」を作りました。
いくつか会社を受けるうえで、パーソルダイバースに入社を決めた理由は面接にあります。ほかの面接では過去の障害について詳細な質問がありました。当社は面接のときにこれからどうしたいかを聞いてくれたんです。
未来のことを聞いてくれたのはなんだかうれしかった。自分の未来を自分で作りたいと思い入社を決めました。

仕事を続ける工夫は「毎日、職場に出社する」ことを優先して生活する
編集部:入社後のお仕事や苦労されたことを教えてください。
森田さん:いまやっている仕事は、オーダーサポート業務といって、企業が人材を募集する際の応募条件や待遇などの必要な項目を、専用のシステムに打ち込む業務です。マニュアルがきちんとあり、その通りにやればしっかりと対応できるので、最初からスムーズに仕事に入れました。一方で集中すると時間を忘れたり、疲れすぎたと思う前に、電池が切れたようにパタリと突っ伏してしまうので、タイマーを使って時間を区切り、定期的に休憩するなど、体調の維持に気を付けていました。

ご飯はパックご飯で済ませ、おかずは買って帰るとか、食洗器をはじめ、自動化できることは自動化しました。もちろんお金が許す範囲で(笑)。
また、睡眠も大切です。熟睡できるようにアイマスクをつける、寝る前にアロマを焚くなど、細かい工夫を重ねています。
繰り返しになりますが、自分にとって一番大事なのは「はたらくこと」。かつては体調を崩してアルバイトを辞め、自宅にいる時、ふと社会に居場所がない、と強烈に孤独というかさびしい思いをしたんです。この気持ちを持ち続けたまま生きるのは嫌だなと思いました。ハローワークに行ったり、就労移行支援事業所に行ったりして、「社会に居場所を作る方法」を素直に学びました。そして、居場所を作る方法が分かって、いまに至ります。最近ではみんなに「明るくなったね」「雰囲気が変わったね」と言われることが多くなりました。
キャリアアップできた理由-「どうしたら効率的にチームに貢献できるか?」を心がけた

編集部:はたらくための準備や努力を怠らなかったのはすごいですね。そして、役職にも就きました。どういう点が評価されたと思いますか?
森田さん:私がはたらくうえで気を付けていたのは次の2点で、そこが評価に繋がったのではないかと思っています。
一つは休まないこと。通院や予定休はしっかり取ります。でも体調不良による突発休を取らないよう、前述のような工夫をしました。予定通り会社にいることで、例えば会議の司会など、いろいろと頼みやすい存在になり、経験が蓄積されたのかもしれません。
もう一つは「今の時間で何をしたら、チーム貢献につながるか」を常に考えていたことかもしれません。例えばこの仕事をすることは、チームにとってどんな意味があるのか、空いている時間があれば、知識を増やすことでチームの価値を上げることはできるのではないか、といったことです。ただ、私は疲れやすい特性があるので、「効率的に全力を注ぐにはどうしたらいいのか」という観点から考えていました。
障害名は同じでも症状はひとそれぞれ違う
サブリーターの仕事をするときに大事にしているのは、メンバーの気持ちのサポートです。自分も精神障害者手帳を持っています。解決できることは多くないですが、実感をもって「分かるよ」と伝えることは結構多いのではないかなと思います。自分も共感してくれると安心するので、そこは忘れないようにしています。
また、「体調が悪化する前に相談してくれるところ」も評価されました。体調が悪くなった後では対応方法の選択肢が少なくなることもあれば、場合によっては長期休暇などに繋がります。それを回避するため報連相を意識していたのが良かったのだと思います。
業務上気を付けていることは、自分の症状とメンバーの症状は決して同じではないかもしれないということです。困っているメンバーを自分に置き換えて考えがちですが、「もしかしたら同じ病名でも症状はまったく違うかも」と考えるようにしています。人それぞれ考え方や性格が違うし、特性も違います。客観的に考えたり、時には上司に相談したりと、常に視野を広くするように心がけています。
はたらくことで、いまの安心感や自信を得ることができた

編集部:とてもご自身を冷静に見ていることに驚きです。入社して3年自分の変化を感じることはありますか?
森田さん:いろいろありすぎて絞れません(笑)。一番大きい変化は「サポートがあれば自分ははたらくことができる」と分かったことかもしれません。はたらくことで今の自信と安心に繋がっているのはとても嬉しいことだな、と感じます。
また、療養中は友人と話すのに気が引けていましたが、いまは堂々と楽しく話すことができます。社会に居場所ができたことで人間関係も変わりましたね。
編集部:今度のキャリアについての考えを教えてください。
森田さん:私は自分の居場所を作りたいと思っていたのと同じくらい、「障害者雇用に貢献したい」と思っています。
パーソルではたらく前は「はたらくことは辛いことで、みんな我慢している。自分はそれができないダメな存在だ」と思っていました。また「自分は何をやってもうまくいかないし、これから先の人生、ますますそうなっていくんだ」と毎日思っていました。でも、いまは「はたらくことは辛いこともあるけれど、それを乗り越えられたら、はたらいて笑えることがある。達成感や満足感を味わうために試練があるんだ」と前向きに考えることができています。
「自分のように変われることができるから」ということを、機会があれば、また必要だと言ってくれれば、自分が発症したときのこと、就職するまでのこと、就職してから長くはたらく工夫を伝えることによって、結果障害者雇用に貢献できればと考えています。
まとめ:発達障害のある方がキャリアアップするために大切なこと
今回、森田さんのインタビューから、発達障害のある方が自分にあった仕事でキャリア形成をはかるうえでのポイントとして、以下のようなことが言えるのではないでしょうか。
- はたらく目的をはっきりさせる:自分は何のために仕事をするのか、はたらく目的は何かをはっきりと持つこと
- 得意を活かす仕事選び:自分の特性を見極め「できること」を軸に仕事を探す
- 安定してはたらく工夫:はたらくことを最優先し、睡眠の質向上や家事の削減など、工夫できるところ見つけ、実行する
- はたらく自信を得ること:「サポートがあれば自分ははたらける」といった、自信や気づきを得ることで安心してはたらくことができる
森田さんは「はたらくことで社会に居場所を見つける」という目的を達成するために、逆算して必要なものを考えて、必要なものを身に着ける努力をいまも行っています。森田さんの姿は、いままさに仕事を探している人、仕事をしたいと考えている人に、参考になるのではないでしょうか。