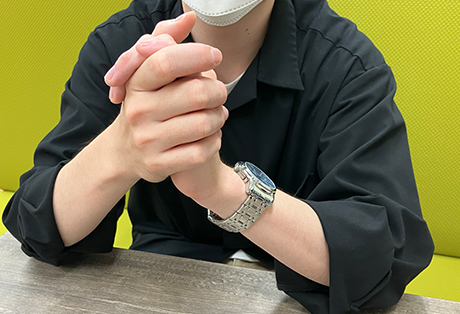パーソルダイバース株式会社で注意欠如・多動症(ADHD)と向き合いながら、大阪西本町オフィスではたらく柴原将大さんは、2020年入社。現在サブリーダーとして、メンバーのメンタルや業務フォローもなども行っています。柴原さんは大学卒業後、一般枠で入社。その後障害が分かり、特例子会社に転職しました。その理由は「自分らしくはたらけると思ったから」でした。
この記事は、ADHDの特性と向き合いながら、安心してはたらける職場環境探しや仕事上の工夫について、柴原さんの実体験をもとに紹介します。

パーソルダイバース株式会社
受託サービス統括本部 受託サービス第1本部
Staffing受託第2事業部
西日本オーダーサポートグループ 第3チーム
柴原 将大
社会人になって気づいた、ADHDによるマルチタスクや会話がうまくできない自分
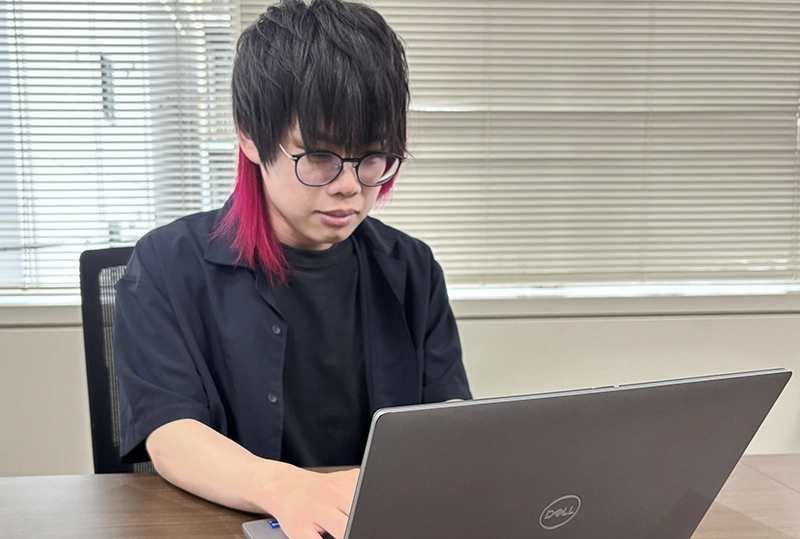
編集部:大学卒業後は一般枠で入社したと伺いました。当社入社までの経緯を教えてください。
柴原さん:2016年に新卒でスーパーマーケットに入社したのが社会人人生のスタートです。その後、大学職員を経て、当社に入社しました。最初の2社は一般枠採用での入社です。社会人として日々はたらく中で自分が苦手なこと、できないことが増えてきて、通院したところ、注意欠如・多動症(ADHD)という診断を受けました。そこで、自分の障害を受け入れてくれて、それでいて自分らしくはたらける場所を探しているうちに、パーソルダイバースに入社を決めました。
編集部:どのようなことが苦手で、できなかったのでしょうか。
柴原さん:タスク管理やマルチタスク、そして特に苦手なのが会話でした。誰かに説明すること、また説明を理解することが苦手で、社会人になって実感しました。それまでも得意ではなかったのですが、就職してからは人と話すシーンが増えて、仕事の進め方が理解できなかったり、上司への報告をうまくできなかったりで、改めて苦手であることと、仕事に支障がでていることを感じて通院を決意しました。
障害が分かったことである意味ホッとしました。決して自分が怠けていたわけじゃないと。それと同時に、配慮を基に自分が活躍できる場所はどこだろうと考えて、一般枠ではなく障害者採用枠、特例子会社への入社を決めました。
台本を作ってリハーサル…ADHDならではの工夫

編集部:入社後の業務と、はたらくうえで工夫していることを教えてください。
柴原さん:2020年に入社後は、パソコンを使っての入力業務を行っています。派遣社員を募集している企業の求人データの入力です。それに加えて、サブリーダーになった2022年からは、メンバーとの面談や、業務レクチャー、業務対応件数などの集計を行っています。
さきほどお伝えした「会話」はいまでも苦手です。サブリーダーになってからは業務説明など、一気にコミュニケーションの機会が増えました。ですから、あらかじめ自分で台本を作って、何回かリハーサルをやって、実際の説明に臨んでいます。台本を書く時間はかかるのですが、台本に基づいて話すと、メンバーがしっかりと理解してくれて、業務を覚えてくれるので、結果的には時間短縮に繋がります。
職場では例えばメモを取る時間を設けてくれるなど、業務を滞りなくするための配慮をしてもらっています。プラスして自分の努力を怠らないことが、長くはたらくコツだと思います。ADHDの特性があったとしても、全部を会社に頼るのではなくて、自分でできる努力を見つけて実行することが大事なのではないでしょうか。おかげさまで、入社後は長期で体調を崩すことなく、心身ともに安定してはたらけていると感じます。
キャリア形成のため、サブリーダーになることを意識して動きました

編集部:現在はサブリーダーという立場ですが、キャリアアップは意識していましたか?
柴原さん:そうですね、最初から何となく意識していました。同期の中で2名仕事ができる人がいて、その2人を意識したというのでしょうか。2人は自分の強みを見つけていって、どんどん成果を残していきました。じゃあ、自分の強みを生かそう、と考えたのですが、なかなか見つからなかった。でも、全国のオフィスを見ると、どんどんサブリーダーになっている人がいました。そこで、「よし、自分は今所属している関西のオーダーチームで初めて手帳を持ったサブリーダーになろう」と決めたんです。
編集部:どんな工夫をしました?上司に相談などしたのでしょうか。
柴原さん:相談すればよかったんですが(笑)、なぜかまったくしませんでした。でも、明らかな強みがなくても、成果を出せば、きっと認めてくれるという上司に対する信頼感はあったので、「じゃあ何をしよう」と自分で考えました。思いついたのは、自分のタスクに加えて、プラスアルファの仕事をするということでした。取り組んだのは、オフィスの留守番電話の解除と設定。これを、障害のある社員だけで回す仕組みとマニュアルと作って実行しました。当社は精神・発達障害の社員が多く、この障害がある人は割と電話対応を含めて、電話に対して苦手意識があるのですが、あえて挑戦。始業時間・終業時間の留守番電話の設定・解除にチャレンジしてみたんです。
一つのプロジェクトを立案して、準備して、実行して、ということをやれば、誰かが見てくれて評価してくれるかも、と思ったんです。実際、これが決め手かどうかは分かりませんが、入社して2年後に無事にサブリーダーになれました。
キャリアアップは自分がやりたいことを実現するための手段と気づいた

編集部:サブリーダーになって良かったですか?
柴原さん:はい、素直に良かったと思っています。仕事の幅が広がりました。これまでやったことがない仕事にチャレンジすることで、自分自身の幅が広がると言いますか、自分の成長を実感できます。最初はサブリーダーになることが目的でしたが、いまはキャリアアップすることで、自分自身の価値が上げられるんだ、ということに気づき、キャリアアップは手段なのかもしれないなと思うようになりました。
ですから、いまも自分自身の価値を高めるために、リーダーなどのキャリアアップを目指しています。自分の仕事をしながら、リーダーのふるまいを横目で見て、「あのリーダーはこう動くんだ、こう指導するんだ」と学んでいます。責任ある仕事にチャレンジするために、勉強したり、上司から学んだり、という過程の中で、自信が少しずつついていくことを実感します。自信がつくことで不安なくはたらける。不安が減ると、安心して長期ではたらける。そんなプラスなサイクルが生まれると思います。
とはいえ、最初からチャレンジするのはたいへんです。自分もそうでした。まずは1年間、目の前の仕事だけをやる、とスタートを切るのはいかがでしょうか。慣れてきたときに、次の風景が見えてくると思います。そのときに、おもむろにチャレンジする。飛び込むことで得られることはあると思っています。これから、仕事をしようとしている皆さん、僕もできたんです、きっと大丈夫!