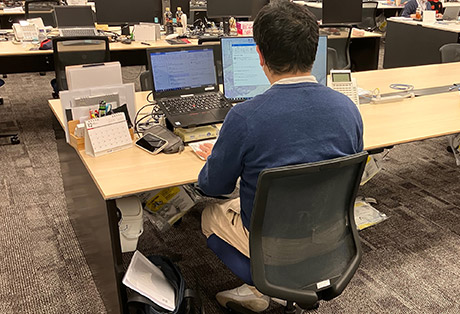パーソルが2022年9月に開催した障害者雇用支援月間特別オンラインセミナー「障害とともに生きる・はたらく 2022 」。今回の記事では、さまざまな分野で活躍する障害当事者が、自身の障害や仕事のこと、職場での工夫などについて本音で語ったセッションの内容を紹介します。
このセッションでは、聴覚障害に関する情報発信やサポートに取り組む株式会社デフサポの代表取締役・牧野友香子さんと、車いすに乗りながらアイドルグループ「仮面女子」メンバーとして活躍する猪狩ともかさんが登壇。お二人のこれまでの体験や現在の活動、障害とともに生きる・はたらくうえで大切なことについてお話を伺い、視聴者から寄せられた質問、悩みにも答えていただきました。モデレーターはパーソルダイバースが運営する「dodaチャレンジ」でキャリアアドバイザーとして活躍する元井洋子さんが務めました。
※本記事は2022年9月に実施したセミナーをもとに執筆しています。役職や取り組み内容などの情報はセミナー当時のものです。
登壇者

株式会社デフサポ
代表取締役
牧野 友香子

猪狩ともか
アイドル「仮面女子」メンバー
モデレータ

パーソルダイバース株式会社
人材ソリューション統括本部
人材ソリューション本部
キャリア支援事業部 首都圏CA第3グループ
マネジャー
元井 洋子
重度難聴の当事者として。難聴の子どもを支援 | 牧野友香子さん
はじめに、牧野友香子さんにお話を伺います。
生まれつき重度の聴覚障害がある牧野さんは大学卒業後、ソニー株式会社に入社し8年間、人事を担当。難病を持つ子ども出産をきっかけに株式会社デフサポを立ち上げました。現在は全国の難聴の未就学児の教育支援や親のカウンセリング事業を行っています。
牧野さん自身の障害やこれまでの道のり、デフサポの取り組みについて伺いました。

「障害の有無は関係ない」に共感しソニーに入社
牧野さん 私は生まれつき耳が聞こえず、補聴器をつけてもほとんど聞こえないくらいの難聴があります。大阪生まれ・大阪育ちの生粋の関西人ですが、就職を機に上京しました。ソニー株式会社で8年間、人事の仕事をしていました。
元井 ソニーには、障害者雇用枠で入社されたのでしょうか?
牧野さん いえ、一般枠です。就活では障害者枠と一般枠の両方から探していましたが、ソニーは「障害の有無に関係なく、対等なレベルを求める」と明言していたんです。それを聞いて「絶対ここに行きたい!」と強く思いました。実際に入社してからも、周囲と対等に扱ってもらい、自由にはたらかせてもらいました。

元井 対等に扱われたからこそ、大変なことも多かったのではないでしょうか?
牧野さん 本当に大変なことはたくさんありました(笑)。業務に関するミーティングは問題なかったのですが、ちょっとした雑談が分からないんですよ。オフィスでは、周囲の何気ない会話を無意識に聞き取って情報を得ることができますよね? でも私は、それがまったく分からない。たとえば、「この人は犬を飼っている」「子どもが2人いる」といった情報は、雑談の中からしか得られません。そのため、コミュニケーションの場面で失敗することもありました。仕事と直接関係がないことだからこそ、周囲に理解してもらうのが難しかったですね。
子どもの難病が人生の転機に
牧野さん そんな中、結婚して生まれた子どもが、50万人に1人の難病を抱えていることが分かりました。育児中には多くの困難を経験し、自分に何かできることはないかと考えるようになりました。その結果、大好きだったソニーを退職し、デフサポを立ち上げる決断をしました。
元井 ソニーで長く活躍し続けるという選択肢もあったと思います。それでも起業を選んだのはなぜでしょう?
牧野さん 正直、辞めるのはとても怖かったです。ソニーは大企業で安定しているし、何より入りたくて入った会社でしたから。でも、デフサポの活動をする中で、耳の聞こえないお子さんを持つ親御さんの悩みを聞いているうちに、「これは副業レベルではできない」と痛感しました。
相談した先輩や同期には、「本気でやりたいならソニーを辞めたほうがいい。ダメになったら戻っておいで」と言われました。その言葉に背中を押され、「えいや!」と決断したんです。
デフサポの挑戦「難聴者のリアルを知ってほしい」
元井 デフサポではどのような活動をされているのでしょうか?
牧野さん デフサポでは、難聴に関する認知拡大を目的に、企業向けのコンサルティングや、難聴の子ども向けのことばの教育、YouTubeでの情報発信などを行っています。
元井 確かに、難聴の方と接する機会がないと、どのようにコミュニケーションをとればいいか分からない人も多いですよね。
牧野さん そうなんです。世の中には聞こえない人がたくさんいるのに、日常的に接する機会がないと、難聴について知る機会がほとんどありません。そのため、いざ出会ったときに、どう接すればいいのか分からない人が多いんです。だからこそ、もっと多くの人に難聴のリアルを知ってもらい、気軽に対応できるようになってもらいたいと思っています。

元井 とても意義のある活動ですね。
牧野さん ありがとうございます! ぜひみなさんも、デフサポのYouTubeチャンネルを登録して、難聴のことを知るきっかけにしてもらえたら嬉しいです!
”車いすのアイドル”として続ける理由 | 猪狩ともかさん
続いて、猪狩ともかさんにお話を伺います。
猪狩さんは2018年4月、強風で倒れてきた看板の下敷きになり、脊髄損傷から下半身不随になる事故に遭いましたが、車いすに乗りながらアイドル活動を再開。「東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」メンバーやNPO法人障がい者e sports全国大会公式アンバサダーなど多方面で活躍されています。
猪狩さんに、ご自身の障害やこれまでの道のり、はたらく想いについて伺いました。

突然の事故から、アイドル活動に復帰できた理由
猪狩さん 私は2018年に強風で倒れた看板の下敷きになり、脊髄損傷による下半身不随となる事故に遭いました。アイドルを目指したのは22歳の時で、それから3年間の下積みを経て、2017年に「仮面女子」の正式メンバーになったんです。埼玉西武ライオンズの始球式にも出演し、夢が叶い始めた矢先の出来事でした。
元井 事故を経て、アイドルを続けるかどうか悩まれませんでしたか?
猪狩さん 周りからも「辞めようと思わなかったの?」とよく聞かれるのですが、私にとってはその選択肢はありませんでした。事故後もメンバーやスタッフの皆さんが支えてくれて、「戻る場所」を作って待っていてくれたんです。そのおかげで、事故からわずか4か月半で復帰ライブを行い、活動を再開することができました。

元井 4か月半での復帰は、とても早いですね。
猪狩さん そう言われることが多いですが、私自身は3か月くらいで復帰できると思っていたので、むしろ遅いと感じていました(笑)。入院中、同じ病室の女性が「この事故のせいで仕事を辞めなければならない、退院後は新しい仕事を探さないと」と話しているのを聞いて、私は本当に恵まれているんだと痛感しました。復帰ライブでは、ファンの皆さんが私の担当カラーの黄色いひまわりを持って迎えてくれて……。その温かい環境があったからこそ、こうして今も「仮面女子」として活動できているのだと思います。
車いすアイドルとしての存在意義を感じ、卒業を撤回
元井 「仮面女子」として活動するうえで、大事にされていることはありますか?
猪狩さん 「仮面女子」というグループの中に、車いすに乗ったメンバーがいる光景は、初めて見る人にとっては珍しいかもしれません。でも、一緒にステージに立ち、フォーメーション移動にも加わるということは、私たちにとってはそれが当たり前なことで、それが自然に見せられるのは、「仮面女子」だからこその強みだと思います。

元井 猪狩さんはアイドルを卒業すると決めた後、ライブで「卒業撤回」を宣言されましたね。続ける決断をされた理由を教えてください。
猪狩さん コロナ禍以降、複数のアイドルグループが出演する対バンライブに出る機会が増えました。そうしたライブ後にSNSを見ていると、「車いすの子が普通に馴染んでいてすごかった」「周りのサポートもすごい」といったコメントがたくさん寄せられるんです。そうした反応を見るたびに、「車いすに乗りながらアイドルを続ける意味」を改めて実感しました。私はまだ、このグループで伝えられることがある——そう思い、卒業撤回を決めました。
元井 猪狩さんの存在が、多くの人に勇気を与えているのですね。
猪狩さん そうであれば嬉しいです。これからも「仮面女子」として、自分にできることを発信していきたいと思います。
障害のある同僚との向き合い方「固定観念をなくし、本人に聞いてみる」
元井 それではここで、視聴者の方から頂いた質問をご紹介します。
一つ目は「障害のある同僚の理解や配慮について、仕事上で気を付けるべきことを教えてください」
まずは牧野さん、いかがでしょう?
牧野さん 人はどうしても障害に対して固定観念を持っています。でも実際には、障害の種類やその影響は一人ひとり異なります。たとえば、難聴の人でも、手話を使う人、補聴器を使う人、読唇術を使う人とさまざまです。だからこそ、一緒にはたらく障害者が何に困っているのか、どんな対応をしてほしいのかを、直接聞いてみるのが一番です。

元井 私も以前、聴覚障害の方と話すときに無意識にゆっくり話す癖があったのですが、牧野さんと初めてお会いした際に「普通に話してください」と言われました。そのとき、同じ障害でも人によって違うのだと気づき、「聞くこと」が大事なのだと実感しました。
牧野さん みなさんは「踏み込んではいけない」と思うかもしれませんが、むしろ「どうしてほしい?」と聞いてくれると、こちらも伝えやすくなります。
猪狩さん 私も牧野さんと同じ考えですね。普段の活動ではメンバーがたくさん助けてくれますが、彼女たちは時間をかけて、私が何に困るのかを知り、理解してくれました。やはり「知ること」が一番大切なのだと思います。
うつ病の友人への適切なサポート「返事を待たない言葉がけ」
元井 次の質問です。「親しい友人がうつ病と診断され、仕事をセーブしていたが、繁忙期になって症状がぶり返してしまい心配している。友人としてどんな声をかけるべきでしょうか?」という内容です。
私はキャリアアドバイザーとしての経験から、同じような状況にあった方々にお話を聞く機会がありました。その中で「返事を待たない言葉がけがすごくうれしかった」という話が印象に残っています。
症状が悪化すると、返信する気力さえなくなることがあります。でも、友人から「こんなことがあったよ。返信はいらないからね。じゃあね」といったメッセージが届くだけで、「私は忘れられていないんだ」と感じられて支えになったそうです。

「いつでも話を聞くよ」と伝えつつ、無理にリアクションを求めずに見守ることが、心の負担を軽くするのかもしれません。
おわりに:知ることから始まる。障害との新しい関わり方
他にも多くの質問が寄せられましたが、1時間のイベントはあっという間に終了しました。
牧野さんも猪狩さんも、難病や、突然の事故によって障害を受傷しても、そのことをきっかけに自分自身の生き方やはたらき方を見つめ、行動している姿が印象的でした。また、そのお二人を取り巻く職場の方や家族、メンバー、スタッフ、ファンの皆さんが、お二人の想いを尊重し、理解やサポートを寄せている様子も伝わってきました。
セッションの最後に牧野さんが「多くの人が障害について知り、気持ちの面でも成熟できたら、きっといい社会になると思う」と話してくれました。
障害とともに生きること、障害のある人を支える方法に正解はありません。障害のある人と関わるとき、特別な配慮が必要だと思い込み、接し方に悩むこともあるかもしれません。しかし、今回のセッションを通じて、「知ること」が何より大切であり、その積み重ねが理解や配慮につながるのだと改めて感じました。
「どう接するべきか」ではなく、「どう知るべきか」から始めること。相手の状況を理解し、負担をかけないコミュニケーションをとれることが、よりよい社会への一歩となるのではないでしょうか。