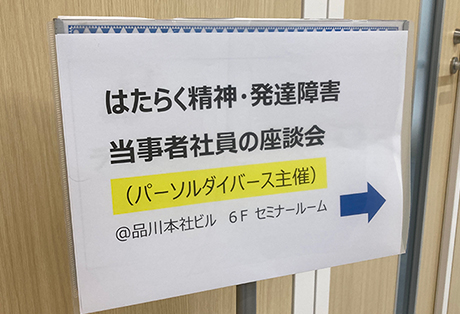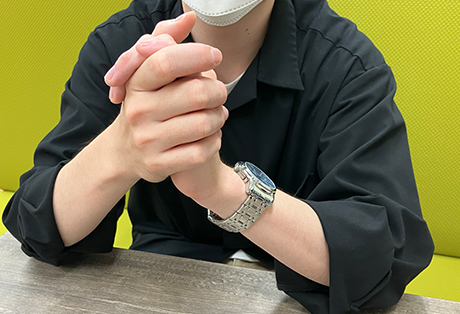先日、パーソルダイバース株式会社において「マスコミ向けの精神・発達障害者向け座談会」というイベントがありました。精神・発達障害がある社員が複数のメディアの方々を前に登壇し、生の声で自分の障害特性や困りごと、その対処方法を話すことにより、メディアの理解醸成を目的にしたイベントです。複数の登壇者のうち、一人は2018年1月に入社した男性社員Tさん。入社当初は、発達障害(ASD=自閉スペクトラム症、ADHD=注意欠陥・多動症)の特性に悩まされ、仕事を覚えるのに苦戦するなど、勤怠や精神状態が不安定で人間関係構築にも悩んでいました。
それが、7年経った今回、記者を前に落ち着いて自分の特性を説明し、いくつかの質問にもアドリブで答えていました。Tさんは、すでに担当する業務でも社内で表彰されるほどに成長していたのです。一体何か彼を変えたのか。その成長の足跡を振り返ってみたいと思います。
最初は攻撃性が強く、社員から相談の声も多かった

ASDやADHD、不安障害や感覚過敏など複数の障害があるTさんには、数多くの特性や苦手なことがありました。入社当初、感情や行動のコントロールが難しく、「暑い」と感じたら、研修中に誰に断ることなくYシャツを脱いだり、研修講師の説明が自分にとって分かりづらいということから、語気を強めて分からない部分を追求したりと、周囲も対応に困るような状態でした。「あの人に研修するのは怖い」と、講師陣から相談があったと聞きました。
そこで、関係者はTさんとの面談回数を増やし、課題点を見つけ、解決を図ることにしました。現場のリーダーや定着支援担当、支援機関が毎月のように面談を実施し、「思ったことをすぐ口にする前に、まずはその言い方で不快感を与えないか考えてみましょう」「相手の言い方が納得いかないときは、まずは大きく深呼吸して、気持ちを落ち着かせましょう」「大きな音が気になるときは、会議室など別の場所に移動することを上司に相談しましょう」などなど、一つひとつの困りごとに対する「答え合わせ」をしながら課題を解決していく日々でした。
このときに行った工夫の一つは、「上長、支援機関、会社の支援担当が必ず同じアドバイスをすること」でした。それぞれがそれぞれのアドバイスをしてしまうと、「自分にとって一番都合の良いアドバイス」だけを受け入れがちになります。周囲の「支える人々」だけで電話やメール、直接会うなど頻繁にコミュニケーションを取り、「●●の相談のときは、●●のアドバイスをする」というすり合わせを綿密に行っていました。
自分の障害特性に向き合うことで、少しずつ状態が上向いてきた

Tさんは、自分の特性理解や業務内容、他者の理解がなかなか進まずに苦労していました。それでも本人は諦めることなく、通常の定期通院に加えて、月に2回のカウンセリングを受け始めました。さらに、支援する関係者同士の連携も継続的に行われています。本人との面談だけでなく周囲からの困りごとに関しても、現場の上長や支援担当が相談に乗り、不安や不満に対する対処法を見つけ、実践することを数年間続けてきました。そして、この数年間の努力が実を結んだのか、少しずつ風向きが変わってきました。
・課題を一つひとつ相談し、その都度解決したこと
・会社・支援者・本人での相談・連携を欠かさなかったこと
・本人が自己理解を進めるため、カウンセリングなど障害に向き合ったこと
・安易に退職を促すのではなく、関係者が粘り強く、支援を続けたこと
これらの積み重ねにより、Tさんは勤続7年を超えました。またTさんも安心してはたらけるようになり、所属する部署から、高いパフォーマンスを発揮したと評価されて月間の表彰者に選ばれました。そして、今回、大手新聞社・通信社の記者の皆さんの前で、堂々と落ち着いて話すまでになりました。
本人と周囲の努力、そして時間が彼の長期就労を実現させた

Tさんは入社当初、ADHDの特性から焦りが強く、「早く仕事を覚えないといけない」「周囲は仕事が速くて自分はだめだ」など、苛立ちを感じては同僚との衝突も何度かありました。
しかしいまは、
・障害特性によるトラブルを短期間でゼロにしようと思わない
・トラブルは自分の特性に起因する場合もあることを自覚する
・比較するのは他人ではない。昨日よりも今日、今日よりも明日、前日の自分を超える
・肩肘張らず、自律に向けた行動を毎日心がける
という気持ちで毎日仕事に向き合っているそうです。数年ぶりにじっくり話をしたTさんは、以前は少々語気も強かったですが、現在は幾分優しくなっていました。また感謝の気持ちを言葉にするようにもなっていました。本人はいまでもまだ他者に迷惑をかけている自覚はあり、「まだまだ自分には足りないことが多い。もっと努力が必要だ」と感じているそうです。
会社という特性上、問題がある社員を長く雇い続けることはなかなか難しいことであるのも事実です。ただ一方で、本人の努力と周囲の環境に加えて時間をかけることにより、当事者の安定就労に繋がるかもしれません。当事者の皆さんは、「自分が変われば、いまの状況が好転するかもしれない」。会社は「もう少し、様子を見てみよう」。このような変化によって、精神・発達障害を持つ社員が長期的に安定してはたらける可能性が高まっていくかもしれません。