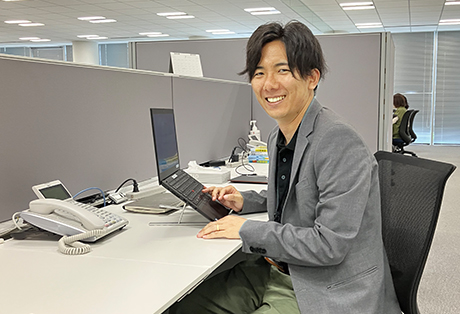パーソルではたらく障害のある社員が、障害についてや職場での工夫、はたらく想いについて語ります。
20代で視覚障害と診断された清宮さん。将来は失明する可能性のある視野狭窄という障害を受傷するも、家族の紹介がきっかけとなりパーソルテンプスタッフに就職。現在は職場の理解を得ながら活躍しています。清宮さんの仕事や職場での工夫、はたらく想いを紹介します。
※本記事は2022年9月に実施したインタビューをもとに執筆しています。

パーソルテンプスタッフ株式会社
清宮 宏章
広域第一事業本部 北関東・甲信コーディネートセンター
2005年入社/網膜色素変性症
視野狭窄による視覚障害を発症「受け入れられなかった」
私が障害を意識したのは28歳のとき。夕立後の薄暗がりの中、自動車を運転していて、右折した瞬間「ドン!」と鈍い音。左から来ていた自転車がまったく見えておらず、事故を起こしてしまったのです。徐行していたので幸いケガ人は出ませんでしたが、大学病院を受診すると「網膜色素変性症」による視野狭窄だと診断されました。

網膜色素変性症は、将来失明の可能性もある病気です。私の場合、視力は悪くなかったのですが、視野狭窄が95%。つまり真正面の5%しか見えていない状態でした。診断を聞いて、結婚したばかりの妻や将来のことが頭に浮かんで「どうしよう」という気持ちでいっぱいに。しばらく仕事も続けていましたが、出勤しようと電車に乗っても会社のある駅で降りられず、そのまま海まで行ってしまったことも。結局仕事はやめてしまいましたが、変なプライドがあったのか、しばらくは自分が障害者であることを受け入れられませんでした。
パーソルテンプスタッフでコーディネーター業務に従事
パーソルと出会いは、パーソルテンプスタッフの派遣スタッフとしてはたらいていた妻の紹介です。最初は乗り気ではなく、とりあえず登録だけしようとオフィスに行きました。すると面接後に担当者の方から「清宮さんはテンプスタッフのコーディネーター業務に合っていると思うので、はたらいてみませんか?」と勧められたのです。
現在はコーディネーターとして100~200名のスタッフさんを担当し、一人ひとりの希望条件・経験を電話でヒアリングし、マッチする仕事を紹介します。また、就業後のフォローやキャリアビジョンのアドバイス、時には顧客企業への営業同行など、さまざまな業務を行っています。
視覚障害による職場の苦労と工夫「聴く力を活かす」
もちろん、見えにくいことでの苦労はあります。例えばPCシステムのバージョンアップや入れ替えなどで、画面操作が変わってしまうと苦労しますね。また、色の識別が難しいため、部屋を暗くして画面を白黒反転させて仕事しています。幸いにも視覚障害向けの便利な機能は世界中で開発しているので、そうしたものも取り入れながら、試行錯誤して業務に取り組んでいます。
ただ、目の機能を失いつつある一方、耳の機能は劇的に向上しました。「おはようございます」の挨拶だけで、声のトーンや抑揚から「いつもとは違うな、何かあったのかな」と感情や調子が読み取れるのです。相手に耳を傾けることが重要になるコーディネーターという仕事にとって、この「聴く力」はとても役立っています。
障害への理解「気遣いや心配りが自然にある職場に感謝」
パーソルテンプスタッフの同僚は気遣いや心配りができるばかりで、人として素晴らしい集団だなと驚きました。メンバーが最寄りの駅で待っていてくれて一緒に出社したり、オフィスで電話中に少し詰まっていると離れた席からサッと駆け寄ってフォローしてくれたり、机の角にぶつからないよう蛍光テープの目印を貼ってくれたり……。一緒にはたらく同僚にとって、視覚障害のある人とはたらくのは初めての経験だったと思いますが、みんな特別な訓練でも受けているのかと思うくらい適切にサポートしてくれます。

以前、社員総会の会場でパーソルテンプスタッフ創業者の篠原欣子さんに肩を叩かれ、「清宮さん大丈夫? 身体だけは気をつけなさいね。」と声をかけてくれたことは今でも忘れません。トップの方から現場の一人ひとりまで、会社全体で人への気遣いや心配りが自然にできる文化が根付いているんだと心から感じますね。
視覚障害者とはたらくために「相手に興味を持って寄り添う」
自分の障害を受け入れてはたらくことは、誰でもすぐにできることではありません。ただ、得意なこと・不得意なことは、障害の有無にかかわらず人間なら誰にでもあるもの。もしあなたが当事者であるなら、不得意なことがあるからといって自分はダメだと思わず、得意なことを見つけ、楽しんではたらいてほしいと思います。それを自分の価値だと思えるようになったとき、喜びや楽しさが生まれてくるのではないでしょうか。
また、障害のある人と初めてはたらく人は、「こんなことを聞いたら失礼かな? 傷つけてしまうかも……」と不安になることもあると思います。しかし大事なのは、健常者/障害者という線引きの前に、人として相手に興味を持ち、寄り添うこと。それによってコミュニケーションが生まれ、お互いの価値観を理解できます。それがやがて、風通しの良い、はたらきやすい環境を生み出していくのだと思います。
障害のある私が思う「はたらいて、笑おう。」
入社以来、本当にたくさんの方々にお世話になって、今の自分がいると感じます。ですから、一緒にはたらく同僚や、企業、スタッフのみなさんなど、私が関わるあらゆる人たちに仕事を通じて恩返しをしたい。それによって相手が笑顔でいてくれたら、それが私にとっての「はたらいて、笑おう。」なのだと思います。

以前、同じ部署の人から「清宮さんと一緒にはたらいたおかげで、目の悪い人の気持ちがわかるようになった。」と言われたことがありました。私自身、自分が障害者にならなければ、街で他の障害のある方を見ても気にも留めなかったかもしれません。こうしたインタビューで自分の存在を発信することが、障害への認知啓蒙や障害のある方々の救いにつながれば、それだけで価値があることだと思います。