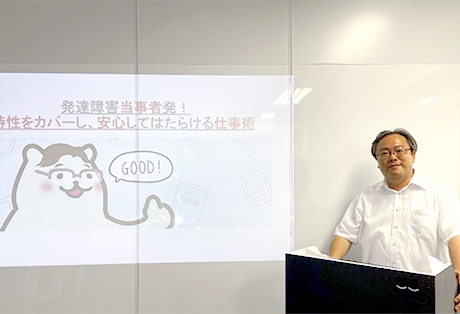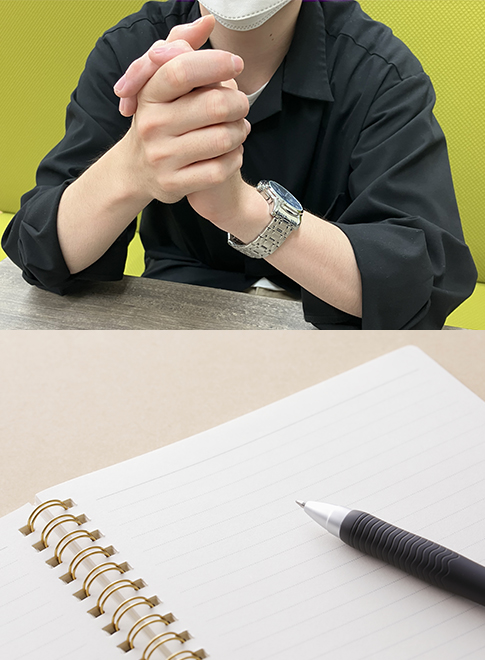
パーソルグループの特例子会社であるパーソルダイバースは、大阪に3つオフィスがあります。その一つ、西本町オフィスではたらくA.Uさんは、2021年10月入社。1年半後にはサブリーダーに着任しました。
Aさんの主な仕事は、パソコンを使った事務入力業務。自身の担当業務をこなすほか、サブリーダーとして配下のメンバーの状態を把握し、業務量の調整や相談対応も行っています。さらに、別事業部に赴き研修講師を務めるなどマルチな活躍も。
Aさんの障害は注意欠陥多動性障害(ADHD)です。ADHD含めて発達障害の人たちは「マルチタスクが苦手」と言われていますが、日常的に多様なタスクをこなすAさん。それを可能にしている工夫は何か、会社の配慮は何か。多方面で活き活きとはたらく姿を見せる秘訣を聞いてみました。
※本記事は2023年8月に実施したインタビューをもとに執筆しています。
パーソルダイバース株式会社
受託サービス第1本部
Staffing受託第2事業部 西日本オーダーサポートグループ 第1チーム サブリーダー
U.A
ミスが多いのは自分のせい? ADHDの診断を受けるまで
編集部 ご自身の障害の診断を受けるまでの経緯を教えてください。
A 小学校5年生のときに担任の先生からADHDの可能性を指摘されました。というのも、極端に物忘れが多かったからです。ただ、当時は発達障害の傾向があっても「障害」として正式に診断されているわけではなく、グレーゾーンの状態でした。そのため、自分の体調に対して特別な関心を持つこともなく、大学卒業まで特に通院はしていませんでした。
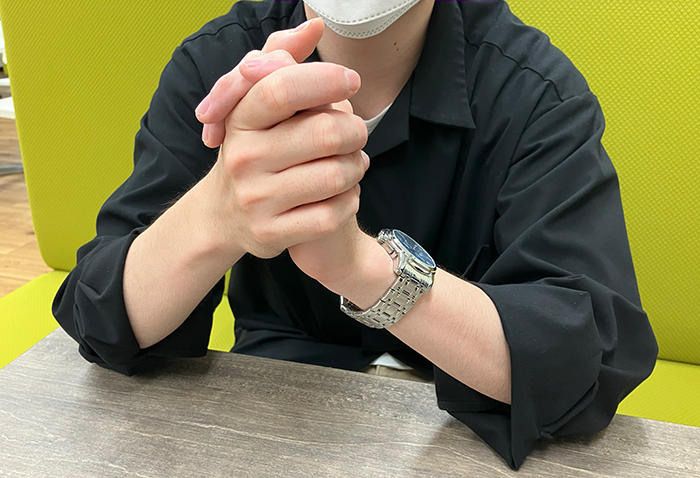
編集部 卒業後は就職されたのですか?
A はい。新卒で小売店に就職し、接客業務を担当していました。しかし、はたらく中でいくつかの「違和感」を覚えたんです。
例えば、商品の発注を忘れてしまったり、大事な作業をすっかり忘れてしまったり、自分が使った覚えのない備品の使用記録が残っていたりと、ミスが頻発しました。結果として、仕事を継続することが難しくなり、規模の小さな小売店へ転職しました。
転職先の店舗はアーケード街にあり、音がこもって響く環境でした。どうやら私には音に敏感な特性があり、雑音が気になると周囲の音に過剰に気を取られてしまうのです。そのせいで指示が理解できなかったり、電話対応ができなかったりしました。加えて、説明を受けても内容が頭に入らないことも多く、インターネットで調べた結果、自分には発達障害の可能性があるのではないかと気づきました。当時の小学校時代のエピソードも次々と思い出しましたね。
編集部 発達障害の可能性に気づいた後、職場に相談したり通院したりしましたか?
A 上司に相談したところ、「言い訳にしかならない」と言われてしまい、受け入れてもらえませんでした。そのとき、「もう退職するしかない」と覚悟を決めました。退職を機に通院を開始し、2020年5月にADHDの診断を受けました。そして同年12月1日には精神障害者手帳を取得しました。
それまでは「自分はおかしいのではないか」と常に不安を抱えていましたが、ミスが多いのは自分の怠慢ではなく障害が影響しているのだと分かって、ようやく安心することができました。
はたらきやすさを求めて特例子会社へ。メンバーのサポート業務を担う
編集部 手帳を取得してから、当社に入社するまでの経緯を教えてください。
A 精神障害者手帳を取得してから、就職活動を続けていましたが、なかなか自分に合った職場が見つからず苦労していました。そんなとき、ハローワークの担当者から、パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業所「ミラトレ尼崎」を紹介されたんです。
正直、それまで就労移行支援事業所の存在も知りませんでしたし、「特例子会社」という言葉さえ初めて耳にしました。でも、少しでもはたらきやすい環境を見つけたかったので、思い切って通所を決めました。

通所を始めてから、支援スタッフの方や同じように通っている仲間たちから、特例子会社について話を聞く機会が増えました。障害特性に合わせたサポートが充実している職場があると知り、「そんなはたらき方があるんだ」と驚いたのを覚えています。次第に、自分も特例子会社ではたらくことに興味を持つようになり、情報収集を重ねました。
その中で目に留まったのが、パーソルダイバースの求人情報でした。「はたらきやすさを大切にしている会社」という印象を受け、もっと詳しく知りたいと思って会社見学に参加したんです。
実際に見学してみると、オフィスではたらいている社員のみなさんがとても笑顔で楽しそうに仕事をしている姿が印象的でした。また、静かで落ち着いた環境が整っており、自分の特性を理解した上ではたらけそうだと感じたんです。「ここなら、自分でも安心してはたらけるかもしれない」と思い、入社を決意しました。
入社後は事務作業を担当しましたが、現在はサブリーダーとしてメンバーへのサポート業務を中心に担当しています。具体的には、入力されたデータのダブルチェックや、健康管理面談を行うことが主な業務です。データ入力では、私たちのお客様であるグループ企業が顧客企業からお預かりした求人情報を取り扱います。仕事内容や給与、勤務時間などを正確に確認し、データベースへ入力していきます。
業務を進める中で感じるのは、サポート体制がしっかりしていることです。困ったことがあれば上司や同僚がすぐにフォローしてくれますし、自分のペースで取り組める環境が整っているため、焦らずに作業ができています。
「細分化して一歩ずつ取り組む」苦手なマルチタスクを克服する
編集部 Aさんはサブリーダーとして、さまざまな業務を抱えながらもしっかり活躍されています。発達障害の方はマルチタスクが苦手な人もいると言われますが、Aさんにはそのような特性はないのでしょうか。
A 複数のことが同時進行すると、やはりいつもよりミスが増えてしまい、とても戸惑います。でも、上司がうまく整理してくれるおかげで、結果的にマルチタスクをこなしているように見えるのかもしれませんね(笑)。
上司から「最初に業務を細分化して、ひとつずつ覚えていきましょう」とアドバイスをもらったことで、少しずつコツがつかめるようになりました。実際に細分化して取り組んでみると、業務を段階的に理解できるようになり、混乱せずに進められるようになりました。
また、メンバーとの面談方法や記録の入力、報告の仕方を覚えることから始め、次に業務量の管理や割り振りの方法を学びました。一つの業務について、1から10までをきちんと習得したら、次の業務へと進むという手順で、一歩ずつじっくり覚えていきました。
編集部 社内の別の事業部で研修講師も務めているとお聞きしましたが、それはどのような内容ですか?
A 研修では「精神・発達障害の人たちとのはたらき方」についてお話ししています。自分自身の経験を通じて、障害についての理解を広げることは、私がずっとやりたいと思っていたことですので、大変さは感じていませんね。
研修講師としての活動は月に1~2回程度で、事前に「この日は参加できますか?」と必ずスケジュールを確認してもらえます。もし都合が合わないときは正直に「できません」と伝えられる環境があり、とてもやりやすいですね。

今後はリーダーとしてさらに成長し、責任感のある大きな仕事にも挑戦していきたいと考えています。
まとめ:マルチタスクが苦手でも大丈夫!Aさんに学ぶ職場選びと仕事術
サブリーダーとして、日々充実してはたらいている様子を笑顔で語ってくれたAさん。「インタビューを通じてこんなに安心してはたらいている自分がいることを、多くの人に知ってもらいたい」と話してくれました。
Aさんの話から、発達障害のある人が、苦手なことがあっても安心してはたらく上でのヒントが見えてきました。
- 「細分化」でマルチタスクを乗り越える
ADHDの特性がありマルチタスクが苦手なAさんは、業務を細分化し、一つずつ覚える工夫をすることで、混乱を減らしながらスキルを身につけていきました。無理に一度に覚えようとせず、段階的に習得していくことがミスを減らすポイントと言えるかもしれません。 - 自分の特性に合った環境を選ぶ
Aさんは自分の特性を理解し、自分にとってはたらきやすい環境は何かを考えた結果、特例子会社を選びました。また、入社前の見学でオフィスの雰囲気やではたらく社員の笑顔に触れたことも、入社の決め手になったと話してくれました。
自分にあった環境を探すこと、自分に合わない環境で無理をしないことが、長くはたらく秘訣と言えそうです。 - サポート体制が整った職場を見つける
Aさんは、パーソルダイバースは業務マニュアルが整備されていることや、上司のサポートがあることで、安心して仕事に取り組めると話してくれました。特に発達障害がある方にとって、「手順や判断基準が明確になっている」「困ったときに相談できる」環境があることが、安心してはたらけるポイントになるでしょう。
最後にAさんは「自分と同じ経験を抱えながら仕事を探している人には、ぜひ当社を推薦したいですね。そして自分と同じ気持ちを味わってほしい」と話してくれました。
withマガジンでは、Aさんと同じく発達障害のある社員のエピソードを紹介しています。また「お仕事図鑑」では、Aさんも従事しているデータ入力業務を紹介しています。ぜひご覧ください。